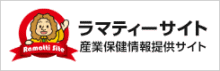九州地方会
2025年10月11日 第57回研究会
- 日時
- 2025年10月11日(土)13:30~17:00 (9:30〜産業医科大学学会)
- 会場
- 産業医科大学ラマツィーニホール 大ホール
&
オンライン(Zoom)
- 共催
- 第43回産業医科大学学会
- プログラム
(敬称略)
- ◇9:30~09:45 開会の辞
産業医科⼤学学会 学会⻑ 上⽥ 陽⼀ (産業医科⼤学 学⻑)
産業医学推進研究会 九州地方会 会⻑ 浅海 洋 (九州旅客鉄道 健康管理室⻑)
◇9:45~10:00 産業医科大学学会総会
◇10:00~10:50 ポスターセッション(現地のみ)
◇11:00~12:15 学会長授賞式および受賞者講演
座長 堀江 正知 (産業医科⼤学 副学⻑)
学会⻑賞受賞者
医学研究分野(論文)
1. 東 泰幸 (産業医科大学 医学部 呼吸器内科)
Inhalation exposure to cross-linked polyacrylic acid induces pulmonary
disorders
架橋型ポリアクリル酸の吸入曝露は肺障害を引き起こす
2. 渡辺 一彦(産業医科大学 高年齢労働者産業保健研究センター)
Daily walking habits can mitigate age-related decline in static balance
: a longitudinal study among aircraft assemblers
静的バランス能力の加齢に伴う低下は日常的な歩行習慣により緩和されうる:航空機組立作業従事者を対象とした縦断研究
産業保健分野(活動報告)
1. 浅海 洋(九州旅客鉄道 健康管理室長)
The Joy of Supporting Workers – Sustained by My Alma Mater and Colleagues
働くことを支える喜び ─ 母校と仲間に支えられて
◇13:30~14:25 産推研九州地方会企画 教育講演
「産業衛生科学科の教育とその社会的役割」
演者 樋上 光雄(産業医科大 産業保健学部 作業環境計測制御学 教授)
座長 浅海 洋(九州旅客鉄道 健康管理室長)
◇14:25~15:15 産業医科大学学会企画 教育講演
「最近の医学部教育の動向と産業医学コア・コンピテンシーについて」
演者 岩田 勲(産業医科大学 医学教育改革推進センター長 教授)
座長 丸山 崇(産業医科大学 医学部 教授)
◇15:30~17:00 産業医科大学学会・産推研九州地方会共催 シンポジウム
テーマ 『産業保健専門職における学部教育の役割』
演者
柴田 喜幸(産業医科大学 産業医実務研修センター 副センター長)
宮崎 洋介(安川電機 統括産業医)
大島 千紗(西日本産業衛生会 保健師)
高橋 一誠(産業医科大学 産業保健学部 産業衛生科学科 助教)
座長
西村 恭子(TOTO 保健師)
江口 尚(産業医科大学 産業生態科学研究所 教授)
- 参加者数
- 127名
(産業医科大学学会のみ参加:26名,
産業医科大学学会と産推研の両方に参加:101名)
- 報告
- 石上 温(産業医科大学 産業保健学部 産業衛生科学科 作業環境計測制御学講座,環マネ5期卒)
2025年10月11日に産業医科大学において開催されました、第43回産業医科大学学会・産業医学推進研究会九州地方会第57回研究会(以下:学会)について報告いたします。
現地では学生を含む多くの方々に、オンラインでも多数の方にご参加いただき、総勢127名(産業医科大学学会のみ参加が26名、産業医科大学学会と産業医学推進研究会の両方に参加が101名)の盛会となりました。
学会の午前の部では、34題のポスター発表と学会長賞授賞式および受賞者講演が行われました。
ポスター発表には研究者・教員だけでなく、多くの学生も参加しており、盛況のうちに活発な意見交換が実施されていました。
私自身も、専門分野以外の研究に触れることで大いに刺激を受け、今後の研究活動に一層励んでいきたいと思っております。
受賞者講演は、
「架橋型ポリアクリル酸の吸入曝露は肺障害を引き起こす(産業医科大学医学部呼吸器内科 東先生)」、
「静的バランス能力の加齢に伴う低下は日常的な歩行習慣により緩和されうる:航空機組立作業従事者を対象とした縦断研究(産業医科大学高年齢労働者産業保健研究センター
渡辺先生)」、
「働くことを支える喜び─母校と仲間に支えられて(九州旅客鉄道 浅海先生)」で、
3名の先生より講演が行われました。
この中の浅海先生の講演の感想について簡単に記載させて頂きます。
浅海先生の講演は、ご自身の体験をもとにしてあり、多くの人にとって非常に参考になる貴重な講演でした。
特に、方針を立てると、物事が動き出す(=活動が進む)という言葉が印象的で、方針を立てる重要性を改めて実感しました。
午前の講義では、今後の教員・研究者人生について、とても有意義な講演を聴講できたと思っております。
学会の午後の部では、
教育講演「産業衛生科学科の教育とその社会的役割(産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科 教授 樋上先生)」、
教育講演「最近の医学部教育の動向と産業医学コア・コンピテンシーについて(産業医科大学医学教育改革推進センター長 教授 岩田先生)」、
シンポジウム「産業保健専門職における学部教育の役割(産業医科大学産業医実務研修センター副センター長 教授 柴田先生、安川電機 統括産業医 宮﨑先生、西日本産業衛生会
保健師 大島先生、産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科 助教 高橋先生)」で、
6名の先生より講演が行われました。
この中の4人の先生が実施したシンポジウムの感想について簡単に記載させて頂きます。
4人の先生の講演より、医学部、看護学科、産業衛生科学科の学部教育は、卒業後にも役立つ、非常に恵まれた教育を受けていると実感しました。
また、医学部、看護学科、産業衛生科学科の卒業生が連携して仕事を行う機会が多いため、学生の時から3学科の繋がりを強化することの重要性を学ぶことができました。
3学科の繋がりを強化するためには、高橋先生がシンポジウムで紹介されていた北里大学のチーム医療論演習が非常に参考になりました。
この演習には1,000名以上の学生が参加し、それぞれの学部の専門性を理解し合いながら、多角的な視点から問題に取り組む重要性を学ぶという内容で、大変興味深いものでした。
異なる学部が協力して行う演習やイベントを、今後、産業医科大学にも取り入れていければと思っております。
午後の講演では、学部教育の意義について改めて考える非常に良い機会となりました。
また、学部教育に特化した講演やシンポジウムを聴講できる機会は非常に貴重であり、多くの参加者が熱心に耳を傾けていた様子が印象的でした。
今後もこのような有意義な講演が継続的に開催されるよう、企画や運営にも積極的に関わり、学会の活性化に貢献していきたいと考えております。