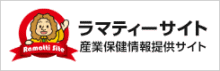九州地方会
2025年7月26日 第56回研究会
- 日時
- 2025年7月26日(土)14:00~16:00
- 会場
- TKP小倉駅前カンファレンスセンター 8階 第8会議室
- テーマ
- 生成AIは産業保健スタッフに有用か ー現場での使い方から、応用可能性までー
- プログラム
- 1.産業保健実務における生成AIの活用
吉武 英隆先生(ダイハツ九州 産業医,医33期卒)
2.産業保健分野における生成AI活用の懸念事項と今後の期待
中尾 由美先生(中尾労働衛生コンサルタント事務所ワーク&ヘルス,専9期卒)
3.生成AIの基礎と最近の活用法
安藤 肇先生(産業医科大学 産業生態学研究所 作業関連疾患予防学研究室 学内講師,医28期卒) - 参加者数
- 31名(産業医5名、産業看護職21名、衛生管理者2名、教員2名、学生1名)
- 報告
- 宮﨑 洋介(安川電機,医27期卒)
2025年7月26日(土)に開催しました、産推研九州地方会第56回研究会について報告いたします。
当日はJR九州が停電により不通となってしまって参加者の来場が危ぶまれましたが、31名(産業医5名、産業看護職21名、衛生管理者2名、教員2名、学生1名)の皆様にご参加いただきました。
本研究会では九州地方会長の浅海先生のご挨拶のあと、3人の演者の方々に「生成AI」についてお話しいただきました。
最初に、吉武英隆先生(ダイハツ九州 産業医,医学部33期卒)より「産業保健実務における生成AIの活用」と題し、産業保健現場で活用できるAIについてお話しいただきました。
吉武先生はAI初学者層をターゲットに「ちょっと使ってみようかな」という動機付けを目的とした内容で、スライド生成AI、画像生成AI、生成AIチャットについて具体的な事例を交えながらわかりやすくご講演いただきました。
CanvaやGammaを用いたスライド作成やChatGPTを使用した画像作成、現場での衛生教育ワークショップを企画する際にチャット形式による生成AIを利用して企画案を練るなど、明日から生成AIに一歩踏み出してみようかなと参加者に思わせる内容で、会場は大いに盛り上がりました。
次に中尾由美先生(中尾労働衛生コンサルタント事務所ワーク&ヘルス,専攻科9期卒)より、「産業保健分野における生成AI活用の懸念事項と今後の期待」をテーマにご講演いただきました。
生成AIはリスク予測・文書作成・教育資料作成など幅広く応用が期待される一方、個人情報保護やハルシネーション、バイアス、過度なモニタリング、判断責任の所在が不明確、プライバシーとセキュリティなどの面で懸念があることも強調されていました。
特に、AIイライザの事件(ある男性が対話型AIとのやりとりを続けた末、自ら命を絶ってしまった事件:ベルギー大手新聞「ラ・リーブル」2023年3月28日)を例にあげ、AIに盲信するのではなく、AIはツールでありパートナーで、AIを使用する側も批判的思考力を身につけ、AIに関する継続的な学習が重要であることを話されていました。
また、産業保健職は人を対象とした健康支援者であり、労働者の安全と健康を最優先に考えながらAIと向き合っていくことの重要性を強調されていました。
そして、安藤肇先生(産業医科大学産業生態科学研究所作業関連疾患予防学研究室学内講師,医学部28期卒)より、「生成AIの基礎と最近の活用法」についてお話しいただきました。
安藤先生には、実際に生成AIによって作成された文章や画像、音声データをご提示頂き、ユーモアを交えながらわかりやすく生成AIの利用について解説していただきました。
産業保健現場での活用用途として、疾患情報収集、法令情報収集、マクロの作成や修正などの補助、海外情報の収集、講話資料作成、資料要約、発表資料のチェック、キーワードがよくわからない情報の収集、といったものが例として挙げられ、より機密性の高い情報を取り扱う場面としては、健診結果からの将来予測や健診データの作成などが想定されることをお話しいただきました。
また、生成AIの注意点として、AIは内容を理解しているわけではなく、入力された質問に対して確率的にありそうなことを提示していることや、それらしい文章を生成しているだけでいかにもそれっぽい嘘を堂々とつくことがあること、インターネットにあまり情報がないとAIの推測が入ること、ハルシネーションを完全に回避することは困難であること、存在しないことでも無理に答えてしまい、まるで存在するかのように回答することがあること、などを事例をもとに解説されていました。
最後に、生成AIは正確性や機能が向上していて利用の幅は広がっているが、業務利用にあたっては機微な情報や業務データでの利用は注意し、あまり機密性が高くないところから触れてみていただきたいとのまとめがありました。
最後の討論の時間では事前に参加者からいただいた質問について3人の先生方に丁寧に回答していただき、盛会のうちに研究会を終了することができました。
先生方には示唆に富んだ実践的な内容をご講演いただき、満足度の高い研究会となりました。
今後も九州地方会では皆様にとって有意義となるような企画を検討していきますので、ぜひ多くの方々のご参加をお待ちしております。