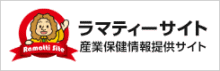九州地方会
2025年1月25日 第55回研究会(2025年 産業保健セミナー)
- 日時
- 2025年1月25日(土)13:00~16:30
- 会場
- TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター 会議室301
&
オンライン(Zoom) - 共催
- 日本産業衛生学会 九州地方会 産業医部会
日本人間工学会
- プログラム
- 第一部:
産業医学推進研究会 九州地方会第55回研究会
「産業保健の未来を共に創る ~人間工学の最前線と新たな挑戦~」
講師:榎原 毅先生(産業医科大学 教授)
第二部:
2023年度九州産業医部会研修会
「産業保健に役立つ眼のはなし」
講師:村上 美紀先生(むらかみ眼科医院 副院長)
- 参加者数
- 105名(現地34名,オンライン71名)
- 報告
- 2025年1月25日(土)に開催しました、2025年産業保健セミナー(共催;日本産業衛生学会九州産業医部会、産業医学推進研究会、日本人間工学会)について報告いたします。
本セミナーには、現地34名、オンライン71名 計105名と多くの方にご参加いただきました。地方会長の浅海先生のサンキューがあふれる投稿に誘われて、思わず申込んでしまった方も含めて、興味をもった方が多くおられたようで、九州以外からも沢山ご参加いただきました。ありがとうございました。
第一部は、産業医学推進研究会 九州地方会第55回研究会として開催し、産業医科大学産業生態科学研究所 人間工学研究室教授 榎原毅先生をお招きしました。
人間工学をテーマにした回は2回目となります。昨年は谷直道先生から腰痛リスク評価を通じて人間工学についてお話しいただきました。今回は榎原先生からお話を聞くことができるとあって、どんなお話が聞けるのか楽しみでもありつつ、難解なイメージが抜けきれず、理解できるか心配・・とやや構え気味だったことをここで告白しておきます。
榎原先生からは、「産業保健の未来を共に創る〜人間工学の最前線と新たな挑戦〜」と題してご講演いただきました。拡大する人間工学の応用領域、普及実装科学としての人間工学〜標準を共に創る〜、産業保健の未来を共に創る〜バックキャスティング型産業保健〜、についてお話いただきました。
拡大する人間工学の応用領域については、虫の眼(一人称の視点)、鳥の眼(三人称の視点)、魚の眼(時間軸で物事をみる視点)を持つことが現在の人間工学の考え方であり、写真で事例を提示しながらわかりやすく説明していただきました。以前は人とモノだけの視点だったが、今はシステム視点で複合的にソリューションを検討することが重要であり、包括的視点で物事を捉えて対処することが人間工学の考え方として求められることを強調されていました。
普及実装科学としての人間工学についての話題では、人間工学研究室が主導しているプロジェクトの紹介がありました。
例えば、ヘルスケア領域では臨床ガイドラインのようなEBMを重視したものがまだ少ないため、Mindsに準拠したガイドラインの策定(陸上貨物運送業の腰痛対策ガイドライン、メンタルヘルスに対するデジタルヘルス・テクノロジー予防介入ガイドライン)についての説明がありました。特に、デジタルメンタルヘルスデバイスについては、どのデジタルヘルスアプリがメンタルヘルス疾患の予防に効果があるかなどについて課題を交えながらわかりやすく説明していただきました。
バックキャスティング型産業保健については、劇的なスピードで技術革新が進む中で働き方は多様化し、後追いの対策では間に合わなくなっていくため、音声感情解析技術の技術革新を例にしながら、先に未来の一時点を考えて(あるべき未来像を設定して)、どのようなことを整備するかを逆算的に考える産業保健の普及実装が重要であることを強調されていました。
榎原先生は、めまぐるしく社会が変わっていくなかで1人の人がすべてのことをマルチにやる必要はなく、パートナーシップで様々な人とともに解決することを提案され、実行されていました。人間工学は様々な領域に親和性があることも分かったので、今後も理解を深めていきたいと思いました。
第一部の後は30分間のティーブレイクがあり、会場ではコーヒー片手に参加者同士の交流と活発な議論が行われていました。
第二部は、日本産業衛生学会 九州産業医部会研修会として、むらかみ眼科医院 副院長 村上美紀先生をお招きして、「産業保健に役立つ眼のはなし」のテーマでご講演いただきました。
事前に質問も多数寄せられており、その内容も踏まえて講義の内容を組んでいただいていました。眼科の復習から始まり、眼科疾患、眼科検診モデル事業とアイフレイル、健康診断と眼科検査と、産業保健で遭遇する眼科領域について多岐に渡って話題提供がありました。
疾患の話では、現場で起こりうる眼外傷について、早急に眼科を受診するべきなのか、それとも待ってもよいのかといったような現場で判断に迷う事例について、対応方法も含めて解説いただきました。色覚異常については、学校で検査が行われなくなっていることから、社会に出て気づくことも多く、どういう組み合わせで起りやすいか知り、対応する方法を身につけさせる必要があること、後天性の色覚異常の検査表は個人の眼科にはないため、必要な場合は大学病院までいかないと検査ができないことなども教えていただきました。また、ドライアイと労働生産性の関係では、ドライアイの治療が労働生産性の改善に有効であるという知見や、作業環境の整備、定期的な休憩(20-20-20ルールの実践)、瞬きの意識、温罨法の実施に加え、健康的な生活習慣が重要であることが強調されていました。
アイフレイルについては、チェックリストを活用した早期発見が有効であることをお話しされ、会場ではチェックリストのパンフレットが配布されました。
パンフレットについてはインターネットからダウンロードできますので参考にされてください。(アイフレイルチェックシート - 日本眼科啓発会議 アイフレイル啓発公式サイト内)
労働に反映する視機能についても解説があり、特に高齢者の視覚特性については今後課題となってくるので、視認性(可視性、可読性、誘目性)を意識して環境を整えることも求められてきそうだと思いました。健康診断と眼科検査については高血圧や糖尿病などの他の検査結果を眼底写真に紐づけて眼科に紹介することの重要性についてお話がありました。どのお話も実際の画像や実例を踏まえて解説いただいたので、早速現場で活かしていける内容を沢山持ち帰ることができました。
お二人の先生方には、分かりやすくかつ実務と今後に活かせる内容をご講演いただき、非常に満足度の高い研究会となりました。誠にありがとうございました。
今回は、久しぶりのハイブリッド開催、かつウェビナー開催ということもあり、運営側も緊張感がある状態でした。とくにダイハツの吉武先生には心理的なご負担を相当おかけしてしまいましたが、笑顔で乗り切ってくださり無事にトラブルなく終了することができました。このように九州地方会は新しいメンバーも増え、にぎやかになっています。また次回も感謝(サンキュー)にあふれた企画をご案内できるよう、メンバー一同進めて参ります。またの皆様のご参加をお待ちしております。