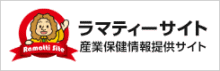関東地方会
2025年7月5日 第87回研究会
- 日時
- 2025年7月5日(土) 14:00~17:00
- 会場
- 日本橋ライフサイエンスハブ 8F
&
オンライン
- テーマ
- 職場の喫煙対策
- 参加者数
- 30名(現地参加22名,オンライン8名)
- 報告
- 小笠原 隆将(三菱ふそうトラック・バス,医27期卒)
2025年7月5日に実施しました、産推研関東地方会研究会の報告です。
今回は職場の喫煙対策というテーマで以下4例の事例報告とグループディスカッションを行い、卒業生全学部1期~40期の幅広い世代で、3時間みっちり職場の喫煙対策について、現地・オンラインの参加の皆様と考える時間となりました。
以下詳細です。
――――――――――――
【前半】職場の喫煙対策にかかる事例報告(4例)
1. 『三菱重工の喫煙対策』
菊池 祐太 先生(三菱重工:医28期卒)
三菱重工は、従業員の健康と快適な職場環境の実現を目指し、2030年度までに「敷地内全面禁煙」を達成する「スモークフリープロジェクト」を推進中であり、その活動の中での取り組み・課題についてお話し頂いた。段階的に禁煙タイムや禁煙デーを拡大し、喫煙所の削減、卒煙支援、啓発教育、オンライン卒煙プログラムを実施。役職者の率先垂範(施策実施の1年前倒しなど)や産業保健スタッフのスキル向上も図り、全社一丸で受動喫煙ゼロを目指している。会社の入っているオフィスの管理会社が異なる場合の施策の難しさ(自社の管理していないビル内の喫煙所で社員が喫煙するなど)をお話し頂いた。
2. 『受動喫煙対策に消極的な職場において阻害要因を一つずつ確認したことで受動喫煙対策を推進した活動報告』
渡辺 麻衣さん(NTT東日本:看19期卒)
NTT東日本の健康管理センタでは、受動喫煙対策に消極的な職場に対し、喫煙環境の実態調査や社員の声の可視化を通じて課題を明確化。総務部や経営層、組合との対話を重ね、喫煙所の1か所集約を実現。段階的な改善を図りつつ、将来的な全面禁煙を目指す取り組みを報告した。
受動喫煙対策の推進について関わる人のスタンスが消極的であったり、会社の経営層会議で全面禁煙が難しいところを個々のキーパーソンに1人ずつ対応しながら丁寧にすすめていった旨を報告頂いた。
3. 『職場協調型禁煙PGの紹介』
横谷 俊孝先生(三菱重工:医29期卒)
日立工場で実施された「職場協調型タバコサヨナラプログラム」は、経営層・現場・産業医が連携し、ニコチンガムの無料配布と講義を通じて禁煙を支援する取り組み。喫煙率の高い職場に対し、教育と補助薬を組み合わせた介入を行い、1年で喫煙率を5%低下させた。今後も段階的な禁煙支援を継続予定。管理・経営層に喫煙率の高さに対して、どう対処したらいいか、という経営層のニーズとして表出させたところで準備した対策を提案する、社員間での喫煙にかかる利害調整したうえで禁煙施策を進めていく際に「産業医をうまくダシに使ってください」のようなフレーズが非常に印象的であった。
4. 『2025年度より開始された敷地内禁煙に対する株式会社SUBARUの取り組み』
奥村 力先生(SUBARU)
SUBARU群馬製作所では、2025年度の完全敷地内禁煙に向け(現在、完全敷地内禁煙実施中)、段階的な喫煙ルールの見直しや禁煙支援施策を展開。従業員アンケートを基に課題を抽出し、産業保健スタッフ主導で禁煙サポートや啓発活動を実施。反対意見もある中、安全衛生委員会との連携を通じて方針を堅持し、喫煙率の低下と健康意識の向上を図っている。社内でのデータ提出の際に、国内のデータを参考に「従業員10000人規模の会社であれば、年間1名喫煙による外で死亡している」というようなインパクトのあるデータ提示の仕方、インパクトが出た他方で、その反響を社内でどのようにコントロールしていくかに課題を感じたなど、社内・社外のデータを常に見合わせながら、経営層含め、社員全体にまず考えてもらう姿勢を発表を通じて感じた。
【後半】グループディスカッション
「職場の喫煙対策のココがツラい/コレいいよ!」
喫煙対策の課題として、組合や経営層に喫煙者がいると施策が進みにくく、加熱式など新型タバコへの知識不足も障壁となる。一方、非喫煙を昇格条件にする、キーパーソンの禁煙支援、職種に応じたアプローチなどが良好事例として挙がった。個別対応や健康経営との連携が鍵とされ、地道な対話と啓発が重要とされた。
「コレいいよ!」で提示された例としては、
・非喫煙であることを昇格条件とする
・キーパーソンに禁煙してもらう
・新卒社員の喫煙開始防止を社内データと照らし合わせながら、経営層の理解を得つつ進めていく
・上記施策をはじめるにあたり、文字通り社内の「火付け役」になる
・新型タバコを含め、タバコのアップデート、喫煙にかかる化学物質(ニコチン・グリセロールなど代謝経路含め)のアップデート・知見も深めていく
・海外でのデータでは医療職の禁煙支援に効果があることが論文等でも示されており、もっと日本でも個別の医療職の禁煙指導に効果があることを推して進めていく必要がある
などなど、非常に多くの示唆に富む議論があった。
――――――――――――
今回の研究会を通して改めて感じたのは、職域における最大の健康リスクである喫煙に対して、組織であれ個人で、まずは1人1人に丁寧にアプローチをしていくこと、そしてあきらめないことの重要性でした。
なお会に先立ちまして大和浩先生(産業医科大学 健康開発科学,医3期卒)から喫煙対策を進めるにあたり、受けられてきた数百の質問を8カテゴリー36のQ&Aにまとめたリンクを共有いただき、こちらも当日参加の会員間で共有させていただきました。(大和先生ありがとうございました!)
こちらより会員登録をすると閲覧できるようになります。
定期開催されている「禁煙推進を考える会」のご紹介も頂きました。
本会後の懇親会も21名の方にご参加いただき、非常に盛況で楽しい盛夏のひと時でございました。
改めましてご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。